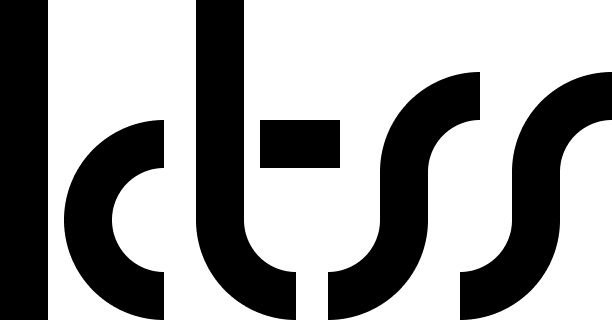コロナ禍を経て、中国からのインバウンド客が徐々に戻りつつある今、日本の多くの事業主や企業が、改めて中国市場への集客・販促戦略を見直すタイミングを迎えています。
とくに、訪日中国人の行動や購買意欲はスマートフォン中心にシフトしており、「ショート動画を起点としたSNSマーケティング」がますます重要になってきました。
しかし中国ではFacebookやInstagram、YouTubeなどの世界的なSNSプラットフォームが利用できません。その代わりに、Douyin(抖音/TikTok中国版)、RED(小紅書)、WeChat(微信)の動画チャンネル、Bilibili(哔哩哔哩)、Kwai(快手)、といった中国独自のSNSが爆発的に発展し、それぞれが独自のエコシステムを築いています。
本記事では?
中国市場向けにマーケティングを検討中の皆さまに向けて、
- 2025年時点で抑えておくべき、中国の5大動画/SNSプラットフォーム
- それぞれの特徴やユーザー層、アルゴリズムの違い
- 企業が参入する上での成功パターン・注意点
- 日本企業による実際の活用事例や傾向
- 最新トレンドと今後の展望
を、なるべく実務・現場目線でわかりやすくまとめました。
こんな方におすすめ!
- 訪日インバウンド需要を取り込みたい飲食店、免税店、小売店、観光施設の方
- 中国マーケットに商品を輸出・販売したいEC事業者
- 中国SNSでのKOL/KOCマーケティングを検討している方
- 自社のSNS運用やプロモーション戦略を見直したい方
比較表:5大プラットフォームの基本情報
| プラットフォーム | 月間アクティブユーザー(MAU) | 主なユーザー層 | 強み | 弱み | 適する業種・商材 |
| Douyin(抖音) | 約8億人 | 20〜40代中心 | 拡散力、EC直結 | 競合過多、広告費上昇 | コスメ、ファッション、飲食、観光PR |
| RED(小紅書) | 約3億人 | 女性20〜30代中心 | 購買意欲高い、口コミ力 | 男性層弱い、UGC依存 | 化粧品、生活雑貨、旅行体験 |
| WeChat(微信) | (12億人ユーザー) | 全世代 | 決済・CRM連動 | 拡散性低め | 飲食チェーン、観光業、既存顧客向け |
| Kwai(快手) | 約3億人 | 地方・中年層 | ライブコマース、地方浸透 | 一級都市で弱め | 日用品、食品、ローカルサービス |
| Bilibili(哔哩哔哩) | 約3億人 | Z世代・趣味層 | コミュニティ | 拡散力は劣る | ゲーム、アニメ、カルチャー商品 |
Douyin(抖音/TikTok中国版) – 圧倒的拡散力とエンタメ性
中国版TikTokとして世界的に知られるDouyinは、月間アクティブユーザー数8億人以上を誇り、20〜40代の若年層を中心に支持されています。ユーザーは都市部に多く、ファッション・美容・旅行・エンタメといったトレンド消費に敏感な層が大半です。主力コンテンツは15秒〜1分程度のショート動画で、音楽やBGMを活用したテンポの良い演出が特徴。さらにライブ配信による「ライブコマース」が定着し、商品紹介からその場での購買までをシームレスに結びつけています。
ユーザー層(年齢・性別・地域・趣味嗜好)
- 月間アクティブユーザー数:2025年には 8.35 億人に達する見込んでいる
- 年齢分布:70%前後が20~40代
- 性別:やや女性寄りだが、男女比は比較的バランスがよい
- 地域/都市区分:一、二級都市に強く、若者が多い地域での利用が一般的
- 趣味・嗜好傾向:エンタメ、ファッション、美容、料理、旅行、ライフスタイル系動画など。コンテンツ探索型・トレンド消費型傾向が強い
コンテンツ形式
- ショート動画(15秒~1分前後):メイン形式。リズム・BGMなどでテンポ感ある構成が強い
- ライブ配信(ライブコマース含む):ライブ形式で商品紹介・販売をする手法が定着
- ハッシュタグチャレンジ、テーマキャンペーン:拡散を誘う企画型施策
- UGC/ユーザー参加型投稿:ユーザー生成投稿がアルゴリズムで評価されやすいため、ブランド投稿+ユーザー参加型企画との親和性が高い
企業活用の成功事例・日本企業実績
- ラグジュアリーブランド:Dior、Chanel、PRADA などがファッションショーのライブ配信、インフルエンサー起用で訴求を拡大
- 地方コンテンツ×農産物プロモーション:農村や地方の特色を活かした動画+ライブ配信で「地方→都市」への知見を引き出す手法が見られる
- MCN と連携したタイアップ施策:多数のクリエイターを束ねる MCN(マルチチャネルネットワーク)を通じて複数アカウントを横並びで運用
- KOL 起用+チャレンジ企画:ブランド・商品をテーマにしたチャレンジ投稿を企画し、ユーザー投稿を巻き込む形で拡散を狙う
広告出稿・プロモーションの特徴(CPC/CTR 傾向など)
- 広告フォーマット:動画広告、ブランド効果広告、ハッシュタグチャレンジ広告、ブランドアカウント強化広告など多様
- アルゴリズム優遇:フォロワー数があるアカウントや認証済み企業アカウントが有利に取り上げられるという報告
- コンテンツ質重視:広告として前面に出しすぎるとユーザーの拒否感を招くため、自然なストーリー性・映像企画力が重要
- ライブコマース併用:ライブ配信と広告を連動させて誘導・転換を図る手法が定番
- 費用指標(参考値):広告単価(CPC/CPM 等)はブランド力・ターゲット設定・競合度合いで幅がある(公開具体値は開示が少ない)
RED(小紅書) – 購買に直結する女性向けSNS
RED(小紅書)は「中国版Instagram+口コミサイト」とも呼ばれ、3億人以上のユーザーを抱えるライフスタイルSNSです。利用者の約8割は女性で、その多くが20〜30代の若年層。都市部在住者が中心で、美容・ファッション・旅行・グルメに関する体験情報やレビュー投稿が人気です。
ユーザー層(年齢・性別・地域・趣味嗜好)
- 性別:女性比率が高く、約8割が女性だったが、近年男性ユーザーも増加傾向
- 年齢:若年層、特に 30歳未満(Z世代含む) が多い
- 地域:都市部中心、トレンド消費力の高いエリア
- 趣味・関心傾向:コスメ、美容、ファッション、旅行、生活雑貨、グルメ、インテリア体験など。レビュー・体験型情報が好まれる
コンテンツ形式
- 投稿ノート形式(写真+テキスト解説):体験レビューを重視した投稿スタイル
- 短動画投稿:映像で使い心地/使用シーンを示す動画
- 口コミ・レビュー:他ユーザー投稿が信頼形成に強く、UGC が重要
- タグ検索/テーマ発見:ユーザーは「次に買いたいもの」「おすすめ〇選」などで検索起点で使う傾向が強い
企業活用の成功事例・日本企業実績
- 旅館・レジャー施設:KOLを起用した投稿で「体験感・宿泊滞在レビュー」を中心に発信。例:温泉旅館が浴衣・施設内体験動画+レビュー投稿
- 化粧品・美容ブランド:日本のスキンケア・化粧品ブランドが RED 上で口コミ投稿+直接購入導線を設け、日本コスメ人気化戦略を取ることが多い
- KOC 活用モデル:多数の消費者に近いインフルエンサー(KOC)を複数起用し、自然投稿風レビューで信頼感を築く手法が増加
広告出稿・プロモーションの特徴(CPC/CTR 傾向など)
- 広告形式:
- 1. インフルエンサー広告(KOL・KOC 投稿形式)
- 2. プラットフォーム内広告(検索リスティング、フィード広告、探索ページ広告)
- 広告感の少ないクリエイティブが有効;あくまで体験視点・共感視点が重視される
- 費用目安(参考):
- CPC(クリック課金):1~3元程度(約20~60円相当)
- CPM(表示課金):1,000回当たり 20~40元程度(約400~800円相当)
- 規制注意:他プラットフォームへの誘導リンクなどは規制対象となる可能性が高い。承認制度あり。
- 広告とオーガニック投稿の併用が鍵:投稿 + 広告のハイブリッド運用が効果を高めやすい。
WeChat(微信)の動画チャンネル
中国で日常インフラとなっているWeChatは、12億人以上のユーザーを持ちます。その中でも新たに注力されている機能が「视频号(Video Channels/動画チャンネル)」です。年齢・性別を問わず幅広いユーザー層が利用し、ニュース、生活情報、エンタメなど多様なコンテンツが視聴されています。
WeChat 自体は SNS+メッセージングが核ですが、近年「视频号(動画チャンネル、Video Channels)」という機能を強化しており、コンテンツ発信 → 流通 → 拡散 → 販売導線を作る上で注目されています。
ユーザー層(年齢・性別・地域・趣味嗜好)
- WeChatは中国の国民的アプリで、全年齢・性別にほぼ普及している(利用率極めて高い)
- 视频号は、WeChatの利用者ベースを活用するため、通常のWeChatユーザー層に共有しやすい
- 趣味・関心方向性は比較的広く、ニュース・生活情報・ブランド発信・エンタメなど多様
コンテンツ形式
- 短動画・ミドル動画:動画コンテンツ発信
- ライブ配信:WeChat エコシステム内でライブ配信 → 視聴・交流
- リンク誘導・ミニプログラム連携:動画チャンネルから WeChat ミニプログラム(EC/予約)へ誘導できる
- 熟人・朋友圈(タイムライン)共有型:WeChatネットワークを通じた“知人シェア”による拡散可能性
企業活用の成功事例・日本企業実績
- WeChatの動画チャンネルはまだ比較的新しいため、事例は限定的だが、既存のWeChat 公号(公式アカウント)を持つ企業が動画号を統合して発信力を高めるケースがある
- 既存顧客コミュニティ(WeChat グループ)との連携で、動画 → ショップ誘導をする企業も見られる
広告出稿・プロモーションの特徴
- WeChatエコシステムと連携できる強み:公式アカウント、ミニプログラム、支払・CRM機能との統合
- 拡散力は抖音などに比べやや劣るが、深い既存ネットワークとの接点強化が目的の場合に有効
- 広告モデル:動画号広告(ブランド動画挿入)・信息流広告(動画形式含む)など
- 成長余力:動画号を通じて動画+広告収益拡大を目指す動きが報告されている
Kwai(快手) – 地方マーケットとライブコマースに強み
Douyinと並ぶ中国の二大ショート動画アプリの一つである快手(Kuaishou)は、特に三級・四級都市や地方部に強い支持を持ちます。月間ユーザー数は3億人以上とされ、年齢層も若者から中年層まで幅広く、生活感あふれる動画が中心。ユーザーは農村や地方文化に根差した日常系コンテンツを好む傾向があります。
(注:「Kwai」は国際版名、「快手」が中国国内名)
ユーザー層(年齢・地域・趣味嗜好)
- 地方都市・三四級都市利用者比率が高い。プラットフォームのコア価値に「すべての人に見られる機会」を掲げており、低所得都市のユーザーも積極に拾う傾向ある
- 年齢層:若年層から中年層まで幅広い
- 趣味傾向:生活密着型コンテンツ、地方文化、日常シーン、簡易料理、地元コンテンツ、ライブ販売
コンテンツ形式
- 短動画 + ライブ配信 を基本二軸とする統合型モデル。
- 強いインタラクティブ性:コメント・ギフト・打賞など視聴者参加型の要素が充実
- 社群/コミュニティ形成:「老铁(ラオティエ)」というファンコミュニティ呼称があり、リピート視聴層をつくる動きが強い。
- ロングテール投稿に強み:大手だけでなく、小規模クリエイターも露出機会が得やすい設計
企業活用の成功事例・日本企業実績
- 地方特産品ライブコマース:農産物、地元加工品などのライブ販売
- 地域観光プロモーション:地域資源を活かした映像+ライブ誘導
- クリエイターと協業した商品タイアップ企画
広告出稿・プロモーションの特徴
- プラットフォームの「公平性」の価値観を前面に打ち出しており、比較的小規模アカウントにも露出機会あり
- 技術インフラとして、分散配信・推薦アルゴリズムによる流量マッチング力を強めている
- 広告形式:動画広告、ライブ流入誘導広告、KOL 提携型広告
- MCNやクリエイターネットワークを介して多点展開するモデルが主流
Bilibili(哔哩哔哩) – 深いファン層とコミュニティ文化
Bilibiliは、中国の若年層カルチャーを代表する動画共有サイトで、アニメ、ゲーム、音楽、知識系コンテンツに強みを持ちます。ユーザーは主に10代〜30代前半のZ世代で、趣味・コミュニティに深く没入する傾向が顕著です。コメント機能(弾幕)や二次創作文化により、ユーザー同士の強固な関係性が生まれやすい点が特徴です。
コンテンツは10分以上の中長尺動画やライブ配信が多く、シリーズ形式の番組やクリエイティブ表現も人気。日本のアニメやゲームはBilibili上で特に人気が高く、公式タイアップやイベント配信も行われています。日本企業では、アニメ制作会社やゲームメーカーが現地ファンとの接点強化に活用する事例が多いです。
広告は趣味セグメントに基づいたターゲティングが可能で、番組スポンサーシップやブランドタイアップが主流。拡散力はDouyinほどではありませんが、ファンとの関係が深いため「長期的なブランド浸透」や「熱量の高いコミュニティ形成」を目的とした施策に向いています。
ユーザー層(年齢・性別・地域・趣味嗜好)
- 若年層・オタクカルチャー・趣味嗜好強め層がコアユーザー
- サブカルチャー、アニメ、ゲーム、クリエイティブ表現、二次創作、知識系コンテンツが得意領域
- 地域的には都市部が中心だが、オンラインでの趣味結びつきが強いため全国展開も可能
コンテンツ形式
- 中/長尺動画(10分~30分、あるいはそれ以上)
- ライブ配信(ゲーム実況、トーク、生配信イベント)
- 番組型コンテンツ、シリーズ企画
- コミュニティ機能:コメント(弹幕)、フォーラム・ファン投稿、二次創作展開
企業活用の成功事例・日本企業実績
- コンテンツスポンサーシップ(アニメ、ゲーム提供元とのコラボ)
- ブランドコンテンツタイアップ(オリジナル番組提供、特集企画)
- クリエイター起用(B 站上の人気クリエイターを使った商品紹介コンテンツ)
- 広告収益・ライブ+付加価値サービス:2022年データで広告収益やライブビジネスが大幅成長
広告出稿・プロモーションの特徴
- 高精度ターゲティング手法:趣味・興味セグメントに基づいた広告配信が比較的効く傾向
- ブランド系広告・動画起点広告・番組スポンサー型広告などが主力
- 他プラットフォームと比べると拡散速度はやや緩やかだが、「長期ファン化」「深い関与」を目的とする施策と相性が良い
まとめ:総合的な比較・注意点・戦略の考え方
拡散 vs 深耕
- Douyin/快手:拡散力重視、バイラル型が得意
- RED/Bilibili:深い共感・レビュー・ファン関係性を重視
- WeChat 视频号:既存ネットワークとの関係強化型
広告・運用コスト vs 効果感
- 拡散重視広告は単価が高まりやすい
- RED や Bilibili は質の高いクリエイティブが求められ、コンテンツ準備コストがかかる
- KOC/中小インフルエンサー併用がコスト効率改善に有効
クロスプラットフォーム戦略
- Douyin で興味喚起 → RED でレビュー信頼化 → WeChat 视频号 に誘導 → 自社ミニプログラム購入導線
- 各プラットフォーム向きのフォーマット・クリエイティブ最適化が鍵